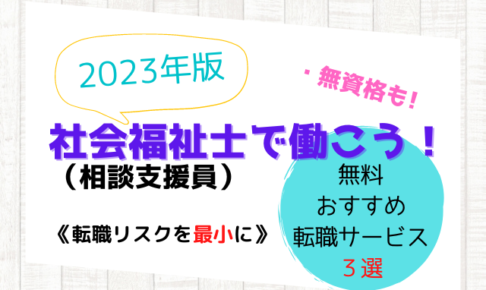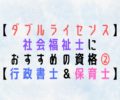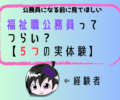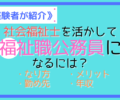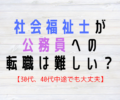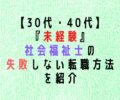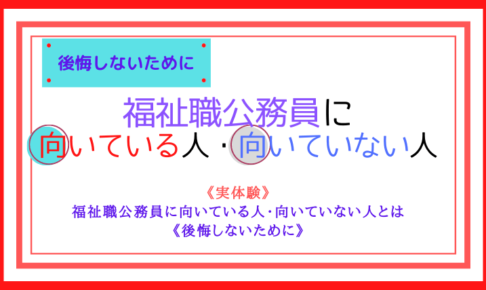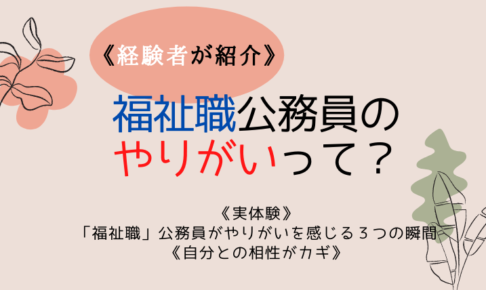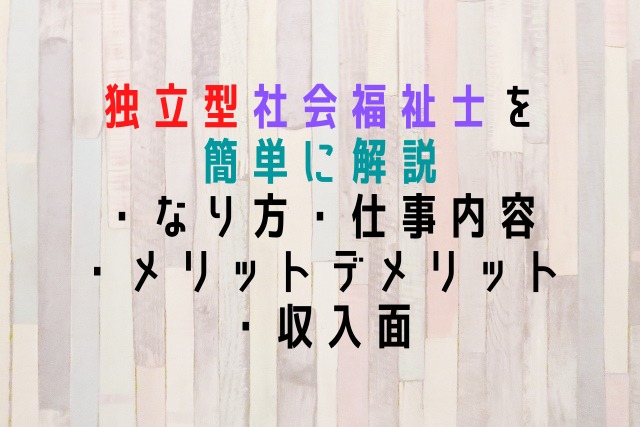

社会福祉士は独立できます。
それは社会福祉士を活かした仕事の記事でも紹介しています。
しかし、独立した場合、どんな仕事をすることになるのかいまいちピンをこない方も多いと思います。
現状、まだまだ認知度の低い独立型社会福祉士。
- 仕事内容
- なり方
- メリットデメリット
- 収入
を解説していきます。ぜひ最後までご覧ください。
この記事の筆者について

新卒でメーカー営業を1年半務めるも挫折、紆余曲折あり福祉施設に8年勤めました。その間社会福祉士を働きながら取得しています。
その後、30代で地方公務員に資格枠(社会福祉士)で採用され今日に至ります。後に精神保健福祉士の資格も取得しています。
実体験を交えながら有益な情報を伝えていきます。
この記事は3分程で読めるようまとめています。最後までお付き合いいただけると嬉しいです。
【こんな方へ】

- 独立型社会福祉士って何?簡単に教えて欲しい
- 独立した場合の仕事内容を教えて欲しい
- どうやったら独立できるのか知りたい
- 独立した時のメリット・デメリットを知りたい
- 独立した時の収入について知りたい
【結論】
- 仕事内容は4種類に大別できる。主な収入は成年後見人報酬
- 独立する方法・独立する際のポイント2つを紹介
- 日本社会福祉士会の名簿登録
- ぱあとなあの登録
- メリット:自由を手に入れ自分のペースで仕事をコントロールすることができる
- デメリット:経済的な保証が一切なくなる。経営者としての能力が必要になり全てが自己責任になる
- 主な収入は成年後見報酬。報酬は月額2万円で毎年一度支払いがある
- 収入を安定させるには社会福祉士以外の資格の資格を活かそう
具体的に紹介していきます
①仕事内容は4種類に大別できる。主な収入は成年後見人報酬
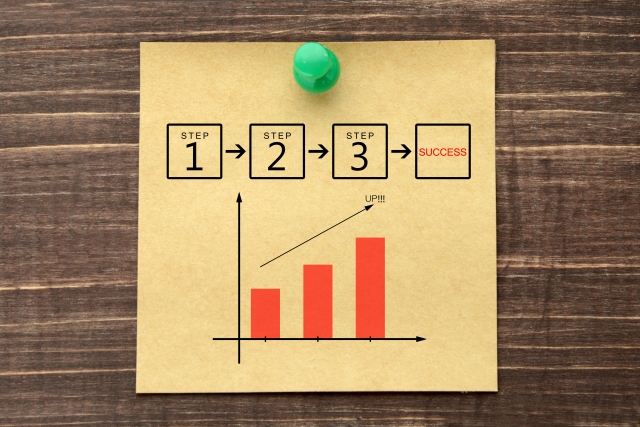

- 独立型社会福祉士って何?簡単に教えて欲しい
- 独立した場合の仕事内容を教えて欲しい
独立型社会福祉士とは
- どこにも所属せず、独立した立場でソーシャルワークを実践する者
- 相談援助の対価として直接、もしくは第三者から報酬を受ける者
独立型社会福祉士とは、どこにも所属せず、独立した立場でソーシャルワークを実践する者で直接的に報酬をもらい仕事をこなしていきます。
福祉で仕事に従事している方はほとんど法人などに所属し業務に当たっています。業務の報酬は法人などを通して間接的に報酬(給与)を貰っています。
独立型は個人事業主(フリーランス)と同じように相談援助において成果を出し、直接報酬を貰う人のことをいいます。
仕事内容
独立した場合の仕事はいくつかあるので、4つに分けて紹介します。
注意したいのが以下の常務を全ておこなう訳ではありません。自分に合ったものや収入を見込めるものを選択する必要があります。
- 1、個人との契約によるもの
- 個別相談
- 援助、見守り
- 家族支援、任意後見、任意代理
- 移送サービスの提供、レスパイトサービスの提供 など
- 2、公的サービスや行政からの委託などによるもの
- 福祉サービス、福祉に関する企画・立案・調査
- 教育機関における講師、講演会・講話 など
- 3、公的サービスや行政からの委託などによるもの
- 成年後見の受任
- 介護保険法や障害者自立支援法に基づくサービスの提供
- 研修による福祉・介護従事者の育成
- 福祉サービス利用援助事業 など
- 4、社会福祉法人・企業・学校などとの契約によるもの
- 福祉サービスの第三者評価
- 福祉などに関する企画・立案
- 教育機関の講師、施設などの職員研修講師 など

②独立する方法・独立する際のポイント2つを紹介


独立だけなら社会福祉士を資格さえあれば可能です。
しかし、現実的にそれだけで収入を得ることは難しく、実質的に日本社会福祉士会の名簿登録と各地域を管轄している「ぱあとなあ」の登録は必要になってきます。
登録することによって仕事の依頼が貰えるなどのメリットが大きいのが理由です。
1、日本社会福祉士会の名簿登録
この名簿登録は強制するものではなく、入らない場合でも罰則はありません。
- 実習生の受け入れ
- 社会福祉士養成課程における相談援助実習を行う実習施設として実習生の受入れを行う場合
- 賠償責保険(独立型)への加入
- 本会の社会福祉士賠償責保険(独立型)Bプランへ加入する場合
会福祉士養成課程における相談援助を行う際の実習施設の1つに「独立型社会福祉士事務所」が位置づけられています。社会福祉士をとる時、実習した方も多いのではないでしょうか。
この実習生の受け入れは独立型社会福祉士名簿に登録が必須条件になります。
また、登録することで「社会福祉士賠償責任保険(独立型)Bプラン」に加入することができます。
リスクマネジメントで保険の加入は必須といっていいでしょう。仕事は全てが完璧なわけではなく、大小問わずミスはつきものです。損害などが発生した時、社会福祉士個人の生活を守ることはできません。そのために備える保険になります。
また、名簿登録にはメリットもあります。
- 社会的信用を得やすい
- 社会的認知のされやすい
- 独立型社会福祉士同士のネットワーク構築
- 社会福祉士養成課程における実習先
- 名簿登録者を対象としたサポート(現在は検討段階)
名簿登録者の情報は本会ホームページ等で公開するため、利用者や関係機関等の方々が独立型社会福祉士に直接アクセスし、閲覧することができます。
本会の名簿登録者は、一定の要件を満たしている独立型社会福祉士であることを社会に広く周知することができ、社会的信用を得ることにもつながります。
「名簿登録者へのサポート」について名簿登録者すると、必要な情報発信等を行っていく予定とのこと。
名簿登録要件はちょっと厳しいです。
- 都道府県社会福祉士会の会員である者
- 認定社会福祉士認証・認定機構により認定された「認定社会福祉士」である者
- 本会へ事業の届出をした者
- 本会独立型社会福祉士委員会主催の独立型社会福祉士に関する研修を修了した者
- 毎年の事業報告書の提出を確約した者
- 社会福祉士賠償責任保険等への加入を確約した者
- 独立型社会福祉士名簿の公開に同意した者
特に②の認定社会福祉士は相談援助実務経験が社会福祉士を取得してから5年以上+その他の要件がありすぐに取得できるわけではありません。
逆に言うと名簿に登録された方は全員認定社会福祉士ということになります。

2、ぱあとなあの登録
「ぱあとなあ」の登録は社会福祉士として成年後見活動を希望する場合登録が必要です。
独立する場合、成年後見人の報酬を当てにする場合が多いです。
超高齢化社会の日本、今後も成年後見人の需要は確実に伸びていくでしょう。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護する制度。
- 社会福祉士国家試験に合格し、厚生労働省に登録済みである
- 自分が該当する各地域のぱあとなあを探す
- カリキュラムの全課程を出席する
- 日本社会福祉士会の基礎課程(基礎研修Ⅰ〜Ⅲ)を修了している者、もしくは日本社会福祉士会の旧生涯研修制度の共通研修課程を1回以上修了している者
- 各地域の要件をクリアする(会費の未納が無いかなど)
注意したいのが④基礎課程(基礎研修Ⅰ〜Ⅲ)です。
基礎研修Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの 3 つの研修からなり社会福祉士として必要な基礎知識を最短で3 年間かけて学ぶ必要があります。同じく④の旧生涯研修制度は2011年に終了しており現在は受けることはできません。

③メリット:自由を手に入れ自分のペースで仕事をコントロールすることができる


自由を手に入れ自分のペースで仕事をコントロールすることができる
独立するということは組織に所属しないということになります。偉い人が決めた方針や上司の意向に従う必要がなくなります。自分を信じ、信念のもと仕事をすることができます。
職場の悩み1位「職場の人間関係」から解放されることになります。
そして、他の資格と組み合わせるなどして、仕事の幅を拡げていき、可能性を広げることができます。
④デメリット:収入・仕事内容全て自己責任になる
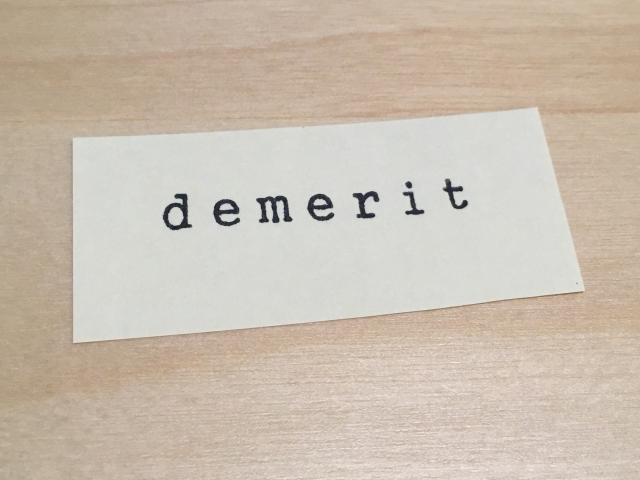
デメリットも紹介します。
経済的な保証が一切なくなる。経営者としての能力が必要になり全てが自己責任になる
どこかに所属しているということは所属先から毎月給料をもらい仕事をしています。
この安定した収入が無くなります。
どれだけの報酬が入ってくるかは本人次第になります。安定した収入を手に入れるめどが必要になります。
また、責任も付きまといます。人と関わる以上、必ずトラブルは発生します。その時の対処は全て自分の責任のもと、解決していく必要があります。

⑤主な収入は成年後見報酬、報酬は月額2万円で毎年一度支払いがある


最後に収入面について紹介します。
独立型社会福祉士の安定した収入になる業務は成年後見業務になることが多いです。
成年後見人の報酬を簡単に分かりやすく説明すると、成年後見人が「報酬付与の申し立て」というものを行い、家庭裁判所が報酬を決定します。基本報酬は月当たり2万円が相場です。
1件の成年後見報酬が2万円なので10件受け持つことができれば月20万の収入となります。
その他の主な収入として研修や講演会の報酬やクライエントからの相談料が挙げられます。事務所の知名度や認知度が重要な要素になってきます。経営手腕を問われる部分でもあります。

収入を安定させるには社会福祉士以外の資格の資格を活かそう
ケアマネジャーを持っている方はケアプランの作成など、毎月固定で報酬が得られる契約をある程度結ぶことで、より安定した収入に繋げられます。
また、ホームを経営するなど別の収入源があるとより安定した経営ができるでしょう。
社会福祉士以外の資格を活かし、多角的に事業経営も検討しましょう。

まとめ

社会福祉士の独立について紹介しました。独立するって勇気が必要です。ですが、既にその一歩を踏み出し独立して活躍している人がいます。
個人的にはもっと広がってほしい働き方です。
- 仕事内容は4種類に大別できき、主な収入は成年後見人報酬
- 独立自体はすぐにできるが①日本社会福祉士会の名簿登録②ぱあとなあの登録を検討しよう
- メリット:自由を手に入れ自分のペースで仕事をコントロールすることができる
- デメリット:経済的な保証が一切なくなる。経営者としての能力が必要になり全てが自己責任になる
- 主な収入は成年後見報酬。報酬は月額2万円で毎年一度支払いがある
- 収入を安定させるには社会福祉士以外の資格の資格を活かそう
以上です。自分に優しい選択を。