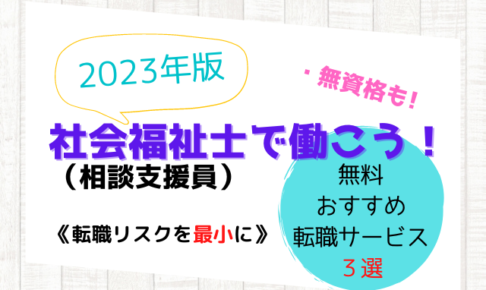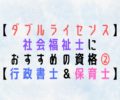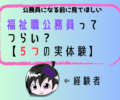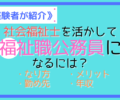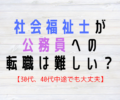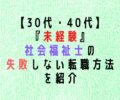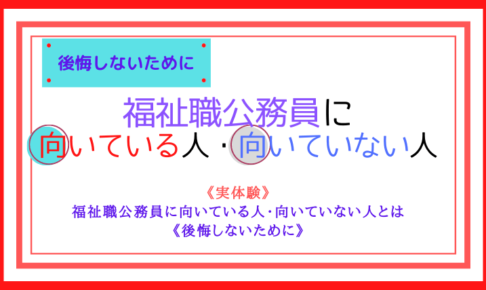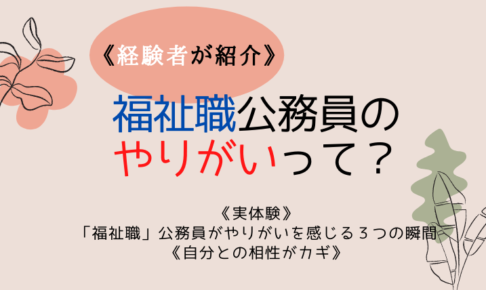- 社会福祉士の仕事ってブラックなの?
- どういう部分で辛い・辞めたいと感じるの?
- 今の職場がブラック。対処法があったら知りたい
よく「社会福祉士ってブラックなの?」と聞かれることがあります。
「医者」「弁護士」のような仕事とは違い、ソーシャルワークの仕事のイメージはしにくいのではないでしょうか。
この記事では社会福祉士(ソーシャルワーク)の仕事のブラックな部分を分かりやすく、実体験を含め紹介します。
- 多くの違う立場の人と関わる機会が多く気を使い疲れてしまう
- 会議の設定、書類作成などの業務で時間に追われる
など、辛いと感じる要素が多いのは事実です。
しかし、辛いと感じる部分もあるひとつの要素がしっかりしていれば解決できます。
それは「働く環境」です。
「働く環境」さえしっかりしていれば、困難なケースも組織として乗り越えることができます。
- 『社会福祉士(ソーシャルワーク)の仕事はブラックなのか』
- 『辛いと感じる実体験3つ紹介』
- 『ブラックな職場と感じた時の対処法』
を紹介します。
実体験を含むリアルな記事になっています。ぜひ最後までご覧ください。
この記事の筆者について

新卒でメーカー営業を1年半務めるも挫折、紆余曲折あり福祉施設に8年勤めました。その間社会福祉士を働きながら取得しています。その後、30代で地方公務員に資格枠(社会福祉士)で採用され、後に精神保健福祉士の資格も取得しました。現在はWEBライターとして生計をたてています。
実体験を交え有益な情報を伝えていきます。
この記事は3分程で読めるようまとめています。最後までお付き合いいただけると嬉しいです。
≪結論≫ブラックはどうかは職場環境(土台)が重要
- プレッシャーや職場環境でブラックに感じる場面はある
- 悩み・苦しみは一人ではなく組織で向き合い解決していくことが大切
- 職場環境が劣悪な場合は早い段階で解決できるように動き出そう。転職も手段のひとつ
社会福祉士はブラックな仕事?実体験3つ紹介


- 資格を活かした仕事ができない
- 絶えず仕事のことが気になってしまう
- 職場に一体感がなく行き詰ってしまう
①資格を活かした仕事ができない

社会福祉士を活かせる仕事となると「ソーシャルワーク(相談業務)」の仕事になります。
- 社会福祉士の資格を持ってるけど介護の仕事をしている
- 相談業務をしたい旨を職場に伝えたがなかなか通らない
など、やっとの思いで資格を取得しても活かす仕事になかなか就けない方が多いです。
実際に求人をみても、介護の仕事なのに「社会福祉士の資格優遇」などの内容をよく見かけます。せっかくソーシャルワーク(相談業務)を志し、苦労してとった社会福祉士という資格を活かしきることができない求人が多いのが実情です。
私自身、以前はこの悩みがずっとありました。
当時、生活支援員をしていた私は職場の上司に「相談業務に挑戦してみたい」と数年にわたり相談していました。しかし、願いは叶うことなく「最終的には転職」という道を選びました。

「社会福祉士の資格を活かせない」というのは仕事のモチベーションが保てない大きな要因でした。
②絶えず仕事のことが気になってしまう

ソーシャルワーカーあるあるだと思います。
相談ケースをある程度任されるようになると心の中に気になる案件が多くなってきます。
- 「あの人、土日問題なく過ごしているかな」
- 「電話したけど繋がらなかった。何かあったのかな」
- 「あのケースの人、トラブル起こしてたから週明けすぐに対応しなきゃ」
など、考え出すとせっかくの休暇が落ち着かず過ごすことになってしまいます。
仕事とプライベートを切り離そうと意識することができれば問題ないのですが、福祉で働く人は気にかかってしまう人や責任感の強い方が多いです。あくまで私の体感上になってしまいますが。
従って、気持ちの切り替えをしっかりとできないと絶えず心にモヤモヤが残ってしまう原因になり、結果的に「辛い、辞めたい」と感じてしまいます。私自身も心配性なことろがあり、担当ケースが増えるたびに悩みが蓄積されていきました。

職場でしっかりと連携できていれば解決の見通しが立ち、休みの日も気が休まらないということは軽減できます。
③職場に一体感がなく行き詰ってしまう

ソーシャルワーク(相談業務)の仕事は相談者(クライエント)の悩み・不安を解決に導くことです。クライエントに対しての悩みや苦悩は正面から向き合っていかなければなりません。
しかし、職場環境は違います。
ソーシャルワーカーはいろいろ機関の協力や理解を得ながらクライエントの問題を解決していく必要があります。このような過酷な業務をひとりだけでこなすことは心身共にもちません。
そこで重要になるのが「職場環境」です。
- 業務で困っていることをなかなか相談できない
- オーバーワーク(長時間労働)をして当たり前の環境
- 組織的ではなくひとりひとりが独自の判断をしている
このような職場は要注意です。
組織的にクライエントの問題に向き合えない職場は相談員自身ストレスを抱え込んでしまいます。それは結果的にクライエントにもソーシャルワーカー自身にもいい影響はありません。

と思うかもしれませんがあります。
私が勤めていた職場がそうでした。相談したくても上司に嫌な顔をされ、結果的に相談できず苦悩する毎日でした。

職場環境がいわゆるブラックな場所に場合は解決方法を考える必要があります。
職場環境(土台)がしっかりしていなければブラックのまま


社会福祉士(ソーシャルワーク)の仕事は見えない部分が多いです。
特にソーシャルワークという仕事は相談を受けた者しか辛い部分は分からず周りにもなかなか理解されず余計に追い込まれてしまうことも少なくありません。
- 自分に自信がなくネガティブ思考の方
- 攻撃的・高圧的な態度の方
- こちらを試そうとする方
など、様々な方がいます。
こういう相談者の対応の悩みというのは社会福祉士として働く以上、向き合っていかなければなりません。しかし「仕事する環境が辛い」という場合は放置せず改善しなければならない要素です。

≪まとめ≫相談者に向き合える職場でブラックな環境から脱出しよう


今回は社会福祉士(ソーシャルワーク)のブラックな仕事なのか紹介しました。
社会福祉士(相談業務)の仕事内容はやりがいがあり、人に感謝される反面、辛い部分も多々あるのは事実です。そんな中、自分の働きやすさはクライエントの満足度に直結します。
仕事内容というより職場環境に原因がある場合は要注意です。出来るだけ早い段階で解決する必要があります。
信頼できる職場の同僚や上司に相談することもひとつの手段です。しかし、職場の雰囲気を変えるって難しい場合が多いと思います。
転職ときくと大きな行動と思うかもしれませんが、まずは相談だけでも大丈夫なんです。外の世界を知り、多くの職場を知ることで新しい発見があるかもしれません。
- ブラックはどうかは職場環境(土台)が大切。こんな状況も土台がしっかりしていれば乗り越えることができる
- 相談者(クライエント)に対する悩みは一人ではなく組織で向き合い解決していくことが大切
- 職場環境が劣悪な場合は早い段階で解決できるように動き出そう。転職も手段のひとつ