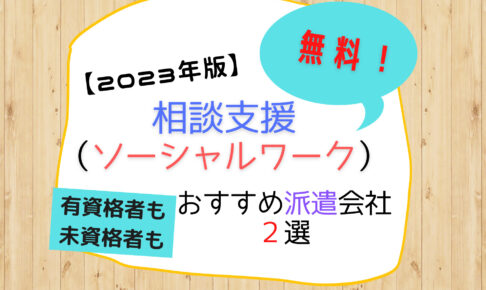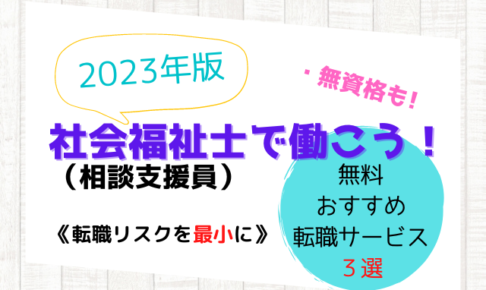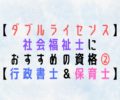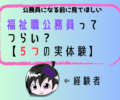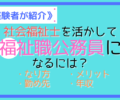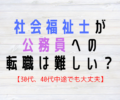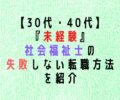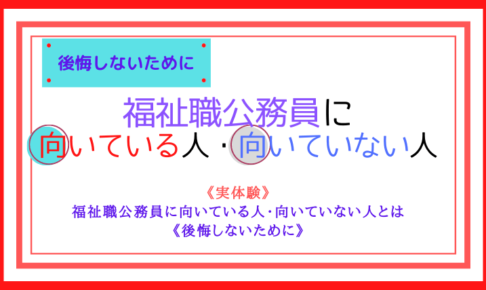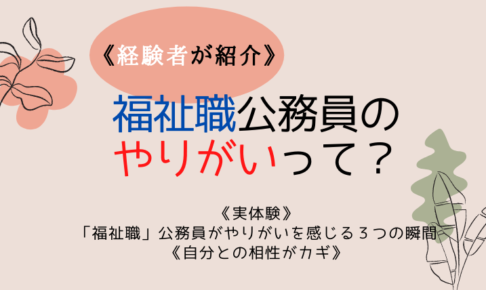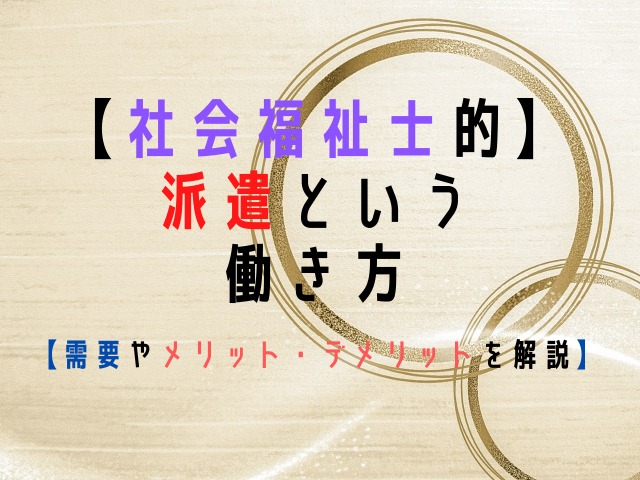

- 社会福祉士資格を活かして派遣の仕事ってできるの?
- そもそも派遣のことがよくわからない。メリット・デメリットを知りたい

多様な生き方が広がる中、派遣という働き方を選択肢のひとつに入れるのはありだと考えます。
現在日本では約40%が正社員ではない非正規として働いており「働き方の幅」は広がってきています。
派遣もそのひとつです。
しかし、派遣という働き方にいいイメージを持っていない方も多いのではないでしょうか。
この記事では派遣という働き方・社会福祉士の資格を活かせるのか・派遣のメリットデメリットを紹介していきます。
この記事の筆者について

新卒でメーカー営業を1年半務めるも挫折、紆余曲折あり福祉施設に8年勤めました。その間社会福祉士を働きながら取得しています。
その後、30代で地方公務員に資格枠(社会福祉士)で採用され今日に至ります。後に精神保健福祉士の資格も取得しています。
実体験を交えながら有益な情報を伝えていきます。
【こんな方へ】派遣って何だろう?社会福祉士は派遣で働ける?メリット・デメリットは?

- 派遣という働き方について教えて欲しい
- 社会福祉士で派遣の仕事ってできるの?
- 派遣社員のメリット・デメリットを知りたい
【結論】社会福祉士でも派遣の求人はある。派遣のメリット・デメリットを理解し、自分に合った働き方を見つけよう
- 派遣社員は、勤め先ではなく派遣会社と雇用契約を結んでいることに利点と欠点がある
- 社会福祉士でも派遣の求人はある。ただし、業務内容に注意しよう
- 派遣のメリット・デメリットを紹介。自分に合った働き方を見つけよう
派遣とは?正社員との違いについて


派遣の大きな特徴としては派遣会社の社員であるということです。
派遣された会社(勤め先)の定める規則や勤務時間で仕事をすることになりますが、給与や保険は派遣会社に従うことになります。
勤め先が雇っているわけではなく、派遣会社と契約を締結し、派遣社員は派遣会社に雇われているのです。
派遣という働き方は、個々のライフスタイルに合った働き方を模索する人がたくさんいる中、注目されている働き方のひとつです。

社会福祉士でも派遣の求人はある。ただし、業務内容に注意しよう


実際に派遣の求人を見てみると、社会福祉士の資格持ちの方の求人はあります。なので一定の需要はあるのは間違いないです。
しかし、業務内容には十分注意してください。
社会福祉士の資格を活かす場合ソーシャルワーカーとして働くことになります。
求人には「社会福祉士」を募集していても、実際の業務内容は介護の募集であることが数多くあります。
これは派遣に限ったことではなく、正社員求人でもよく見かけるので気を付けてください。
社会福祉士の資格活かしたい場合は、相談員・生活相談員などの名称で募集しているところを探しましょう。

派遣のメリット・デメリット

派遣のメリット

- 自分の時間が持てる(定時で帰ることができ、サービス残業が無い)
- 仕事の悩み・問題が解決しやすい
- 時給単価が高い
- 自分の希望シフトで働け、時間を有効に使える
①自分の時間が持てる(定時で帰ることができ、サービス残業が無い)
派遣は勤め先に雇われているわけではありません。
派遣会社と勤め先の法人が契約して労働時間や賃金を決定しています。
つまり、日本企業特有の「サービス残業」することはありません。
もちろん、派遣で働く方も与えられた業務をしっかりとこなす必要がありますが、過度な仕事量でない限り、時間内で終わるでしょう。
②仕事の悩み・問題が解決しやすい
仕事の悩みって必ずありますよね。
よくある悩みが「人間関係」
直接雇用されていると「言いづらい」「言ってもどうせ解決しない」ということも多いと思います。
勤め先に言いにくいこともまずは派遣会社に相談し、派遣会社から勤め先に連絡してくれます。派遣会社なので相談しやすく、積極的に解決を促してくれます。
時給アップの交渉もしてくれるところもあります。
③時給単価が高い
アルバイト・パートと比較すると時給単価が高いです。一概には言えませんが+300~500円多く受け取れるところもあります。

一番の理由は働いているところで直接雇っていないからです。実は直接働きたい人を探し、雇うというのはコストがどうしてもかかります。
- 採用するまでのコスト
- 社会保険料
- もろもろの手当など
派遣の場合は上記のようなコストはありません。従って派遣として働く方はその分給料に上乗せされやすく、時給が上がりやすい仕組みになってます。
④自分の希望シフトで働け、時間を有効に使える
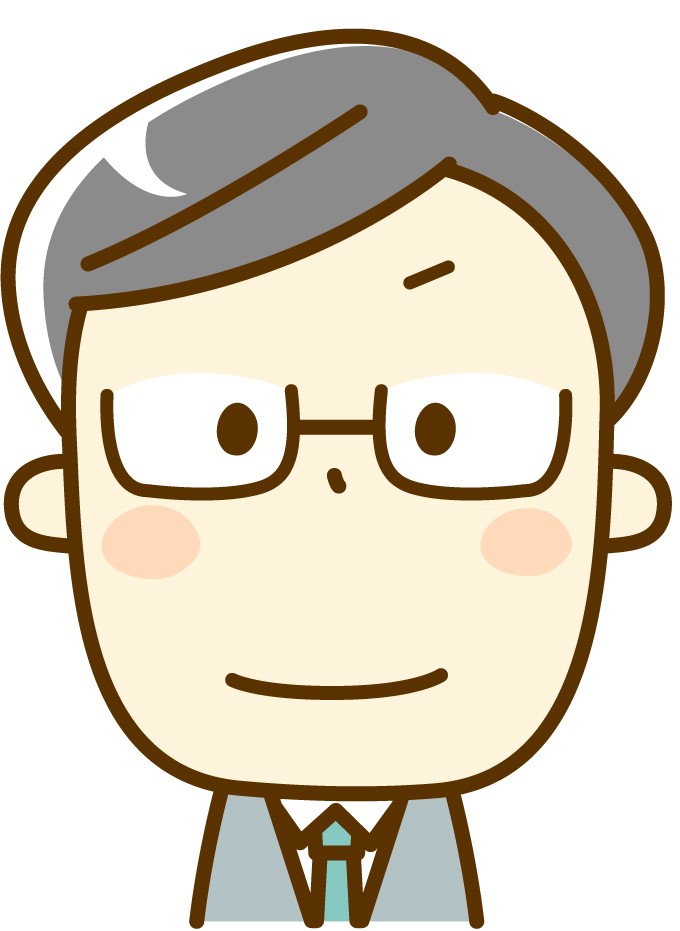
言われたことがある方も多いのではないでしょうか。
派遣の場合はこういったことはありません。
会社と会社で契約している以上、事前に派遣会社と話し合って決めた勤務日数・時間で働くことが前提です。
また、有給の取得もとりやすく、派遣会社に相談することで希望日を伝えることで職場に過度な遠慮はせず休むことができます。

派遣のデメリット
- ボーナスが出ない
- 正社員よりも福利厚生がやや薄い
- 同じ職場で働き続けられない可能性がある
- 社会的地位が低くみられる
①ボーナスが出ない
一般的に正社員には年に2回ボーナスがありますが、派遣社員にはありません。
これは大きなデメリットに感じる方も多いでしょう。
参考に派遣で働いた場合の年収を計算してみました。現役で働いている方は今の収入と比べてみてください。
- 一日8時間労働 1,500×8=12,000円
- 週5日労働 12,000×5=60,000円
- 一か月の4週間 60,000×4=240,000円
- 一年間働いた場合 240,000×12=2,880,000円
年収でいうと2,880,000円ですね。
今の自分の収入と比べてどうでしょうか?
介護業界全体の年収は他の業種に比べ高いと言えません。もし、あまり差がないなら派遣の道も選択肢にいれてみてはいかがでしょうか。

②正社員よりも福利厚生がやや薄い
実は派遣会社の福利厚生、基本の福利厚生は「正社員」並みに整備されています。
- 交通費
- 社会保険(健康保険)
- 厚生年金
- 有給休暇
- 健康診断 など
派遣をしている方が受けれる一般的な「福利厚生」です。逆に上記の福利厚生が無い派遣は避けた方が無難かもしれません。
デメリットで挙げた理由は「住宅手当」「出産手当」などはないことが挙げられます。この部分はそもそも直接雇われている場合でもないところもあるので微妙なところでもあります。
③同じ職場で働き続けられない可能性がある
派遣社員は、派遣先事業所の同一の組織単位(課やグループなど)で、3年を超えて派遣就業することはできません。なので「ここの職場でもっと働きたい」と思っても3年以上は働けない可能性があります。
ただし、俗にいう3年縛りも以下の場合は対象外となります。
- 派遣元で無期雇用されている
- 60歳以上
- 終期が明確な有期プロジェクトに派遣される
- 日数限定業務(1ヶ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下)
- 産休・育休・介護休暇などを取得する人の代わりに派遣される
このような方は継続して働くことができます。

そんなことはありません。
現在は派遣会社は派遣社員に対し、雇用の安定化措置を実施することが義務付けられました。
派遣会社は以下の①~④の順番で、派遣スタッフが希望する措置を行うように努めなければなりません。
- 派遣先への直接雇用を依頼
- 新たな派遣先の提供(能力・経験などに照らして、合理的なものに限る)
- 派遣元での無期限雇用
- 安定した雇用の継続を図るための措置(教育訓練や、紹介予定派遣など)
派遣雇用の安定は問題視されており、改善されています。全く仕事がなくなるといったケースは防げる可能性は高くなっています。
④社会的地位が低くみられる
日本において、正社員に比べ社会的地位は低いということは否めません。
特に影響する部分は「結婚するとき」と「ローン審査」。
結婚を考えていて、相手の両親に仕事が派遣だと知られると、いい印象は得られないことをよく耳にします。考えが古いと言えばそれまでですが、結婚は慎重になる人生の転換期。いい印象を与えられない可能性があります。
また、住宅などを購入する時に活用することになるローン。ここでも職業は重要は要素です。派遣だから絶対無理というわけではなく、勤続年数や収入から審査するローン会社も増えてきています。
まとめ

今回は「派遣」にスポットをあて紹介しました。記事をつくってて感じたことがあります。

そもそもサービス残業ないのが当たり前だと思いますし、自分の時間が持てるなどもあって当然なのかなと。働きやすい環境に改善していくことを願っています。
特にメリット①で挙げた自分の時間が持てるのは大きな利点だと思います。
- 資格などキャリアアップ
- 副業
- 趣味
- 友人や家族との時間
などの時間にあてられワークライフバランスを保ちやすくなります。
これを機会にこれからの働き方について考えてみてはいかがでしょうか?
- 派遣社員は、勤め先ではなく派遣会社と雇用契約を結んでいることに利点と欠点がある
- 社会福祉士でも派遣の求人はある。ただし、業務内容が「介護」になっている場合も。相談員として働きたい場合は事前に派遣会社に伝えることを忘れずに
- 派遣にはそれぞれメリット・デメリットがある。これを機会に自分に合った働き方を見つけよう
以上です。自分に優しい選択を。