

社会福祉士の活躍の場は日々広がっており、公務員においても社会福祉士を資格要件とする自治体が増えています。
この記事では、福祉職公務員を経験して実際に経験したメリット・デメリットを紹介します。
公務員の就職、転職を考えている方は有益な情報ですので、ぜひ最後までご覧ください。

※下記のコンテンツから好きな見出しにスキップできます
この記事の筆者について

その後、30代で地方公務員に資格枠(社会福祉士)で採用され今日に至ります。後に精神保健福祉士の資格も取得しています。
実体験を交えながら有益な情報を伝えていきます。
【結論】メリットが大きい反面デメリットも。自分に向いているか見極めよう
- メリット
- 給与・福祉厚生が充実しており、業務により集中できる
- 転職しなくても多分野の経験を積める
- 行政の仕組みを深く知ることができる
- デメリット
- ひとつの分野に特化することは難しい
- 年功序列の組織体制
- 複数の役割分担を与えられることがある
福祉職公務員になる3つの《メリット》


- 給与・福祉厚生が充実しており、業務により集中できる
- 転職しなくても多分野の経験を積める
- 行政の仕組みを深く知ることができる
①給与・福祉厚生が充実しており、業務により集中できる
公務員は安定して給料が入るため所得面は安定します。福利厚生についても一般水準と同等かそれ以上なのでそういった意味でも安心できます。
自分の生活が不安定で悩みを抱えてしまうと、他人の援助どころではなくなってしまいます。
また、滅多なことが無い限り、クビといったこともな福祉業務に集中しやすい環境といえます。

生活基盤が安定し、援助に集中できるということは相談援助を続けていくうえで大きなメリットになります
②転職しなくても多分野の経験を積める

普段働いている中で↑のように感じたことはありませんか?
これは公務員全体に当てはまることではないですが、市町村などの地方公務員になった場合、定期的に異動が伴います。そのため、転職しなくてもさまざまな分野の業務に携わることができます。
社会福祉士で採用された場合「福祉職」として採用されているので
- 高齢
- 児童
- 障がい
など、福祉に関する課の異動がほとんどです。

③行政の立場から福祉と向き合い、行政の仕組みを深く知ることができる

福祉の相談業務をしていくうえで行政サービスは切っても切れません。どこで福祉サービスで働いたとしても必ず何かしら行政のサービスを利用することになるといっていいでしょう。
公務員になることで嫌でも行政の知識は身についていきます。上にも挙げた通り定期的に異動もあるので知識の範囲は広がっていきます。
経験は自分の価値を高めてくれる重要な要素です。働きながら行政の仕組みが分かるのは一石二鳥といえます。

福祉職公務員になる3つの《デメリット》
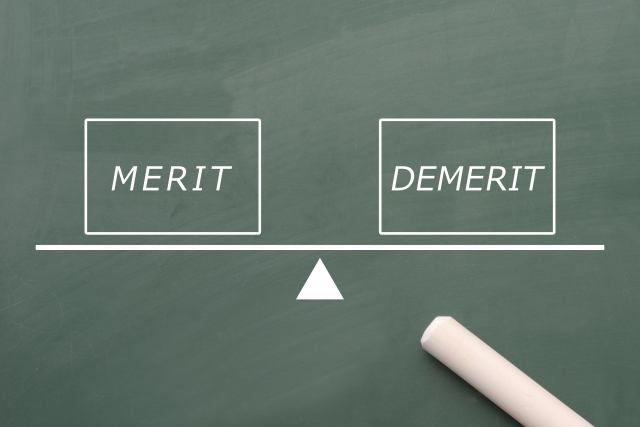

最後にデメリットについても紹介します。
- ひとつの分野に特化することは難しい
- 年功序列の組織体制
- 複数の役割分担を与えられることがある
①ひとつの分野に特化することは難しい
公務員には定期的に異動があり、これは社会福祉士など福祉枠で採用された場合でも例外ではないことが多いです。基本的に数年ごとに異動になるので、異動先では新しい制度などの知識を学ばねばなりません。
1つの分野を極めたいと思う方にとって異動がネックになる可能性があります。

②年功序列の組織体制
公務員は年功序列の仕組みが色濃く残っています。
年功序列とは、年齢や勤続年数に応じて、役職や賃金を上昇させる人事制度のこと。
勤続年数を重ねるほど一定の役職につき賃金も上がる仕組みです。能力の高くない人が役職を上がっていくことで新人部下に悪影響を与えてしまうことも。
年功序列制度により人材を確保しやすくする手法は、日本的経営の特徴です。一方、民間企業では「成果主義」を取り入れている一般企業も増えてきましたが、公務員はいまだに年功序列の風土が残っているところが多いです。

③複数の役割分担を与えられることがある
特に規模の小さい自治体だと当てはまります。
近年、公務員の数は減少しており、業務の兼任は珍しくありません。したがって、福祉以外の仕事も任される可能性が高いです。
政令指定都市などの大きな自治体では専門で任されることも聞きますが、規模によっては複数の仕事を任される可能性があることを覚悟しましょう

なので「福祉業務にだけ集中していればいい」という訳ではなく、自分なりのペース配分を掴むことが必要になります。
《私の場合》公務員を辞める選択をした
私は最終的に公務員を辞める選択をしました。
理由は、今記事で紹介したデメリットの部分を強く感じたからです。年功序列的風土が残っているところで、残業も毎日のようになりました。
結局メンタルが持たず、退職の道を選びました。
公務員に強い憧れを持っている方も少なくないと思いますが、公務員にも向き不向きがあり、仕事はそれだけではありません。
「なんとなく公務員になろうかな」という理由だけでは、私のように挫折してしまう可能性もあります。自分が将来どんな風に生きていきたいのか、一度考えてみることをおすすめします。

まとめ

実体験から、社会福祉士が福祉職公務員になり感じた3つのメリット・デメリットを紹介しました。
公務員にも向いている人とそうでない人がいると思います。今回紹介したメリット、デメリットを比べ、自分が公務員に向いているのか考える機会にしていただければ幸いです。
- メリット
- 給与・福祉厚生が充実しており、業務により集中できる
- 転職しなくても多分野の経験を積める
- 行政の仕組みを深く知ることができる
- デメリット
- ひとつの分野に特化することは難しい
- 年功序列の組織体制
- 複数の役割分担を与えられることがある
もし公務員に興味がある方がましたら別記事も参考にしてみください。


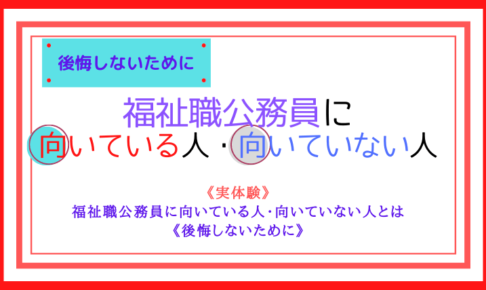

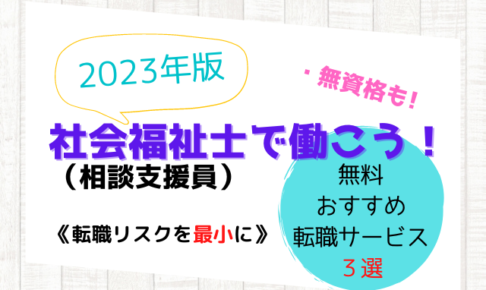

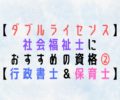
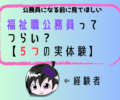
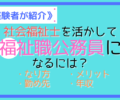
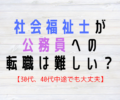
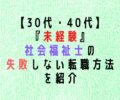


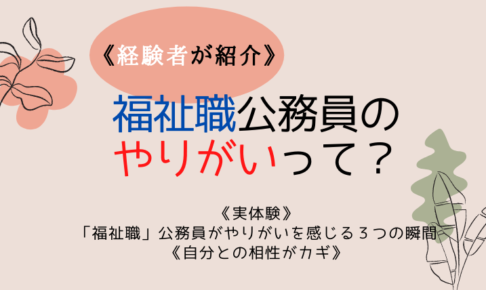


公務員になった時にどんなメリットがあるのか知りたい