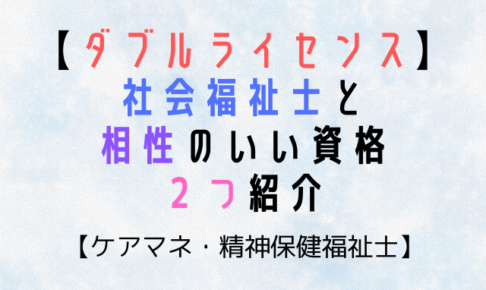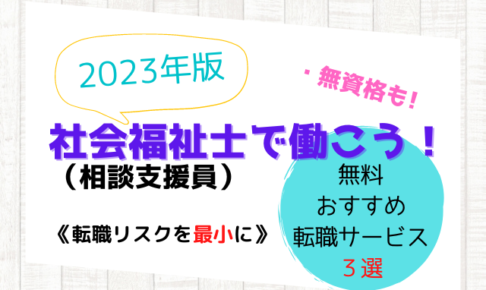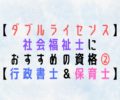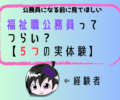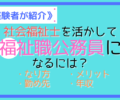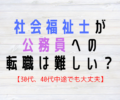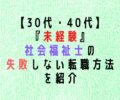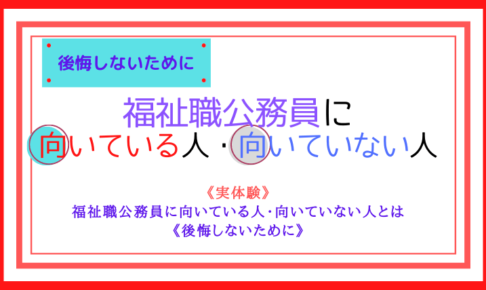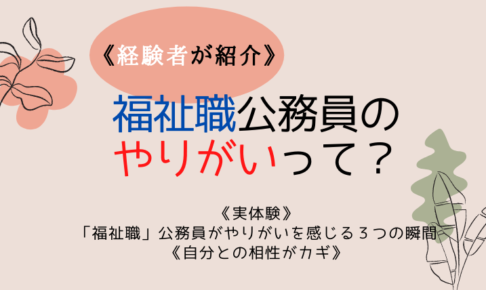- 社会福祉士を活かせる資格を探してる
- キャリアアップしたい。社会福祉士と相性がいい資格を知りたい
社会福祉士(相談支援員)として活躍する中
- 自身の価値を高めるため
- 将来のキャリアアップ
など、ダブルライセンス取得を検討している方も多いと思います。
そこで今回は、社会福祉士におすすめするダブルライセンスの資格のうちおすすめの資格2つを紹介します。
将来のステップアップで資格の取得を目指している方、ぜひ参考にしてください!
※前回の記事もありますので、興味があればぜひご覧ください。
コンテンツ
この記事の筆者について

新卒でメーカー営業を1年半務めるも挫折、紆余曲折あり福祉施設に8年勤めました。その間社会福祉士を働きながら取得しています。
その後、30代で地方公務員に資格枠(社会福祉士)で採用され、後に精神保健福祉士の資格も取得しています。
現在はWEBライターをしています。
実体験を交えながら有益な情報を伝えていきます。
この記事は3分程で読めるようまとめています。最後までお付き合いいただけると嬉しいです。
【結論】行政書士と保育士は社会福祉士との相性◎
- おすすめ資格① 行政書士
国民と行政のパイプ役で福祉と法律のスペシャリストになれる!独立も視野に
- オススメ資格② 保育士
児童を対象とした知識を深めたい方におすすめの資格
社会福祉士と相性がいい資格① 行政書士

①行政書士とは
国家資格である行政書士は、法律に関する高度な知識が求められ行政に関わる申請業務に携わる資格です。
行政書士が独占する業務+他の資格で独占されていない業務があり、非常に広い範囲で活躍できます。
仕事内容は大きく3つあり
- 「書類作成」行政に関わる書類の作成
- 「許認可申請の代理」申請を代行して行う
- 「相談業務」相談を受け、アドバイスを行う
が主な仕事内容になります。例を上げると
- 遺言作成
- 相続分割協議
- クーリングオフ
といった業務をしている行政書士の方もいます。

②相性がいい理由
-
生活の問題解決に直結しやすく、社会福祉と親和性高い
-
受験資格のハードルがなく受験しやすい
-
2つの資格を活かし独立を視野に入れられる
①生活の問題解決に直結し、社会福祉と親和性高い
社会福祉士と行政書士とのダブルライセンスがあれば、行政書士の知見により具体的な解決策を提案できるようになります。
相談内容は介護面だけではなく・生活費・家族関係、自分が亡くなった時のことなど、行政に関わる様々な悩みを抱える場面に遭遇することは決して少なくありません。
また、相談職として成長するだけでなく、転職する際の強みになる点もおすすめできる要素です。
②受験資格のハードルがなく受験しやすい
行政書士は、合格率こそ10%ほどと少ないものの、実務経験や教育機関での受講がなくても受験可能で、働きながらでも取得しやすい資格です。
詳しくは③資格をとる方法で紹介しますので参考にしてください。
③2つの資格を活かし独立を視野に入れられる
社会福祉士と行政書士のダブルライセンスにより、独立での事務所を構えることも可能です。
案件ごとに社会福祉士か行政書士、どちらか(あるいは両方を)で対応するか自分で選ぶことができ、スピーディーに対応できるようになります。
③資格をとる方法
資格を取得するには以下の3つの方法があります。
- 行政書士試験に合格する
- 一定期間公務員としての勤務を経験する
- 弁護士・弁理士・公認会計士・税理士のいずれかの国家資格を取得する

行政書士試験に受験資格はなく、受験事態のハードルは低いです。(実際に登録できるのは20歳からになります)
- 毎年1回
- 11月の第2日曜日 午後1時から午後4時まで
- 憲法
- 行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法が中心)
- 民法、商法及び基礎法学の中からそれぞれ出題
法令については、試験を実施する日の属する年度の4月1日現在施行されている法令に関して出題
- 政治・経済・社会
- 情報通信・個人情報保護
- 文章理解
④注意点 合格率は約10%と試験は難関
試験の合格率は10%代を推移しており、難しい部類になる試験です。
目安となる勉強時間は500時間~800時間といわれており、計画的に試験対策をすすめていく必要があります。
しかし、受験資格が特に無く、受験者数が多いため合格率が低めになっている可能性があります。合格率が低い分、合格した時の時の恩恵は大きいです。

社会福祉士と相性がいい資格② 保育士

①保育士とは
保育士は、乳幼児の保育のプロとして主に保育園で子どものお世話をする職業です。
乳幼児を預かるだけが仕事ではなく
・食事や排泄、着替え等の補助、リクリエーションなどを通して基本的生活習慣や社会性を身に付けさせていきながら、一人ひとりの発達を考慮して保育計画を保育をおこないます。
保育をおこなうえで仕事内容は多岐に渡り
- 計画や活動の記録
- 子どもの発達記録などの書類作成のほか
- 行事の企画・運営、遊びや教材等の準備
など、多くの業務が求められます。
また、乳幼児の保護者への保育指導も行える立場とされて、 児童福祉法に基づいた国家資格となっています。
②相性がいい理由
- 児童に関するより専門的な知識を身につく
- 活かす職場がたくさんある
- 受験が年2回で受験ハードルが低め
①児童に関するより専門的な知識を身につく
近年、放課後デイサービスなど児童に関連する施設が急増しています。
保育士の資格は、これから新しく児童・家庭福祉分野への転職をかんがえている方には、社会福祉士と保育士のダブルライセンスにより転職先へのアピールをしやすいです。
また、近頃は児童に関する相談業務においても強い専門性が求められるようになってきています。
- 核家族
- シングル親家庭増加
- 虐待やひきこもり
などの問題を抱えている児童・家庭は、これからますます専門性の知識を求められる場面が多くなってくることが予想されます。
また、近年では医療的ケアを必要とする幼児も増えています。
保育士の知見に基づいた知識+経験と、社会福祉士としてのソーシャルワークによる解決する力があれば、仕事に活かしやすくなります。
②活かす職場がたくさんある
保育士が活躍できる職場はたくさんあります。代表的な保育園、保育所の他に
- 児童養護施設
- 知的障害児施設
- 知的障害児通園施設
- 盲ろうあ児施設
と、社会福祉士の関係する職場の多くあることが分かります。このような職場に特に興味のある方はおすすめです。
③受験が年2回で受験ハードルが低め
保育士の試験は、4月と10月の年2回あり、資格取得のチャンスが多いです。詳しくはこの後の③資格をとる方法で紹介します。
③資格をとる方法
- 大学・短期大学・専門学校など、厚生労働大臣が指定する「保育士を養成する学校その他の施設」で必要な科目を履修し卒業する。または保育士国家試験を受ける
- 国家試験を受ける場合4月頃(前期)と10月頃(後期)の年に2回実施
- 試験は筆記試験と実技試験があり、筆記試験に合格した人のみ実技試験に進む
保育士資格を取得する方法は
- 保育士養成校(大学や専門学校)に通って卒業と同時に取得する方法
- 国家試験を受験して取得する方法
の2通りがあります。
国家試験を受験するにはいくつか要件があり、ここでは詳しく触れません。
詳細を知りたい方は一度調べてみることをおすすめします。
保育士国家試験は
- 子ども家庭福祉
- 社会福祉
など、社会福祉士と深く関係している科目が含まれており、児童福祉分野をより深く学ぶことができます。
④注意点
- 子ども家庭福祉専門の国家資格の新設が検討されている
日本では現在「子ども家庭福祉」の国家資格の創設が検討されている段階です。
(参考:厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kodomo_554389_00011.html)
現在社会福祉士をお持ちの方で、児童分野についてより学びたい方は、保育士資格の取得を目指すのもひとつの手ではありますが、子ども家庭福祉資格が今後どうなっていくか動向を見守ってから検討してみる必要があるかもしれません。
まとめ

社会福祉士の仕事は、日々現場で複雑な課題を抱えてる方も少なくないことと思います。
そんな中、働きながらでも何とか資格を取得を目指しキャリアアップを目指すことは素晴らしいことです。現在の業務に活かすことはもちろん、将来のキャリアアップを考えながら自身にマッチした資格を検討してみてはいかがでしょうか。
- おすすめ資格① 行政書士
国民と行政のパイプ役で福祉と法律のスペシャリストになれる!独立も視野に
- オススメ資格② 保育士
児童を対象とした知識を深めたい方におすすめの資格
- 自分の価値を高めるためにもダブルライセンスを検討しよう

関連記事もありますのでぜひ参考にしてみてください。